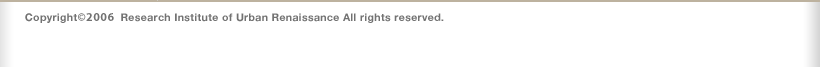| ◇少子社会対応委員会 3ヵ年の活動結果 | ||||
| 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | シンポジウムの開催 | 小冊子の発行 |
少子社会対応委員会(平成16年度の活動)
少子社会対応委員会(平成17年度の活動)(1)少子化とは何か。
一般的に、「少子化」とは「合計特殊出生率が人口の置換水準を下回る現象」をいいます。わが国の少子化を取り巻く現状としては、①子どもの絶対数が少なくなっている、②出生率が低下している、という2つの現象が進行していることを整理しました。
(2)わが国における少子化の現状と背景
日本における少子化の現状とその社会的背景を整理し、「女性の社会進出」、「若者の将来不安」、「出生率そのものの低下」が大きな要因となっていることを整理しました。
(3)欧米諸国における少子化の動向
少子化は、日本に先んじて欧州諸国で進んでいる減少です。そこでの少子化対策は、家族政策として位置づけられています。そこで、フランスとスウェーデンにおける少子社会対応策の現状を調査しました。
その結果、わが国の子育て環境の整備は遅れていることが克明になりました。社会的支出において、わが国は依然として高齢者への所得移転に大きな比重が置かれており、社会保障給付金に占める高齢者関係給付費の割合は児童・家族関係給付費の約18倍(2002年)となっています。児童手当に関しても欧州諸国における年齢制限は早くて16歳未満であり、わが国の3歳未満という条件はかなり特異といえます。そして、給付条件についても、欧州諸国では所得により金額差はみられるものの、所得制限を設けている点も珍しいことがわかりました。
(4)少子社会に関する意識調査
インターネットを活用して、少子社会に関する意識調査(回答数2000)を実施しました。その結果、約7割の人が重要な問題と認識しており、少子化対策として①子育てに係る経済的な負担の軽減、②保育サービスの充実が求められていることがわかりました。
(5)少子社会問題に関する論点
少子化は、女性の社会進出、若年層の経済的不安、子育てに係る経済的負担感、仕事と子育ての両立への負担感、子どもをもつことに対する個人の意識変化など、さまざまな要因が絡み合っていることがわかりましたが、少子社会対応策を検討するためには、①急激な少子高齢社会への移行による社会保障制度の対応遅れ、②子育て支援や社会の理解不足等による少子社会の悪循環が論点であることがわかりました。
平成16年度調査概要 [PDFファイル:467KB]
少子社会対応委員会(平成18年度の活動)(1)少子社会に関する長期予測
2005年の国勢調査の結果が発表となり、日本の総人口が初めて減少しました。合計特殊出生率は1.26と過去最低を更新し、厚生労働省の人口動態統計速報値では、初めて出生数が死亡数を下回る自然減となりました。
それに伴い、2050年には女性が40%も減少し、人口置換水準に戻っても子どもは減ることがわかりました。
(2)少子社会が社会経済情勢に及ぼす影響
急激な少子高齢社会への移行による社会保障制度の対応の遅れが大きな課題であることから、少子化が歳入・歳出、社会保障給付金、年金制度、医療制度、介護保険制度に与える影響分析を行いました。
(3)海外にみる少子社会への対応状況
フランスとイタリアにおける少子社会対応状況を調査しました。特に、市民に対するインタビューを行い、少子化問題に対する認識が深く、社会全体の課題として取り組んでいることがわかりました。
(4)わが国における少子社会への対応
少子社会が社会経済環境に与える影響分析から、社会全体で子どもを育てるパラダイム転換が必要であり、特に①出産・子育てが不利にならない社会づくり、②子育てが負担にならない家庭像の構築、③少子社会に対応した都市・住宅政策への転換などへの取組が必要であることを提言しました。
また、シンポジウムを開催し、わが国における少子化問題への取組が喫緊であることを訴えました。
平成17年度調査概要 [PDFファイル:775KB]
(1)日本企業における子育て支援の状況調査
これまでの研究成果を踏まえて、少子社会対応策としては「育児と仕事の両立」、「ワーク・ライフ・バランスの実現」が重要であることから、日本企業の子育て支援の実態をヒアリング/アンケート調査しました。その結果、福利厚生制度として子育て支援策が講じられているが、実際の取得率をみると、男性の育児参加が少ないことがわかりました。
(2)フランスにおける子育て支援の状況調査
フランスの民間企業・病院・託児施設運営会社に対して、子育て支援の状況を調査しました。その結果、「社会全体で子どもを育てる」という認識が企業を含めて醸成されており、各種家族協会を通じて政策決定に市民の意見が反映されていることがわかりました。
(3)少子社会対応のための政策提案
3年度にわたる調査研究の成果として、少子社会対応策として次の7点の政策提案を行いました。
- 少子社会対応への国民のコンセンサスづくり
- 子育てと仕事の両立が可能な就労環境づくり
- 地域による子育て支援
- 多様な家族形態が認められる子どもを持ちやすい社会環境づくり
- 妊娠・出産の安心・安全の確保
- 社会保障給付費に占める児童・家族関係費の増大
- 市民の意見を政策に反映させる仕組みづくり
平成18年度調査概要 [PDFファイル:325KB] また、シンポジウムを開催し、わが国における少子化問題への取組が喫緊であることとフランスを参考にした少子化対策が必要であることを訴えました。平成19年4月には3年度の成果を踏まえ、少子化の問題を広く啓発するため「2050年のニッポン・ハッピー化計画」という小冊子を発行しました。